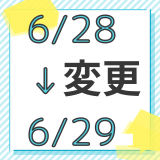前回・その1のおさらい
前回・その1の到達目標は次の内容です!みなさんはできるようになりましたか~?
- パルマを叩く姿勢が猫背ではなく、凛とした姿勢を保てる。
- ブレリアの12拍子について、足でアクセントを入れて表拍の手拍子(パルマ)が叩ける。
- ブレリアの12拍子について、足でアクセントを入れて裏拍の手拍子(パルマ)が叩ける。
- お友達と「表拍」「裏拍」の役割分担をもって、それぞれがつられないで手拍子(パルマ)を叩けるようになる。なお、練習のときには、足ではブレリアの12拍子についてアクセントを入れる。
今回やること
上記1~4ができるようになったら、引き続き手拍子(パルマ)なのですが、次の場所を意識して叩けるようになる、というのが次の到達目標です。
意識するポイントとは次のとおりです。
これがわかるようになると、フィン・デ・フィエスタブレリアの音源だけ聞いていても、踊り手がどういう動きをしているかというのがなんとなく想像がつきます。
また、これらを意識して、YouTubeなどの動画を観るとよいと思います!
- 踊り始めの場所がわかる
- カイーダの「10」の場所がわかる
この2つを具体的に説明してみますね。
踊り始めの場所がわかる
これには2つの意味があります。
まず1つめは、歌い手さん・カンテが歌っているときとか、ギターさんのファルセータのときは、まだ、カンテさんやギターさんの「番」なので、踊り手は踊り始めまない、ということです。
カンテさんが、出だしのサリーダを歌っていたり、または、ブレリア1つはまるっと歌うときもあります(踊り手が踊らずに)。そういうときは、カンテさんの「番」だから、踊り手は邪魔をせず、素敵な歌だな、かっこいいな~と思いつつ、ハレオやパルマでカンテさんを讃えて盛り上げます!
この時に「自分はいつ踊り始めたらいいのかしら…」とドギマギしちゃったり、「いつ入ろう・いつ入ろう」みたいに長縄に入るタイミングを待つ感じ…みたいになっちゃうと、カンテさんの歌に集中してないな~というのがあからさまにわかってしまいます。
なので、踊り始めの場所がわかれば、まずはカンテさんの歌を楽しく聴くことができるようになります!
これはカンテさんの歌だけでなく、ギターさんのファルセータも同じ。
ギターさんがフィエスタブレリアの際に、めちゃかっこよきファルセータを弾いてくださったときは、やはりそれはギターさんの「番」なので、踊り手は踊り始めません。
パルマ・ハレオで盛り上げます!
そして2つめの意味。
それは、踊り手のブレリアの始め方には、2つのパターンがあるということ。
- パターン1 踊り手が「ジャマーダ(llamada)」を出して歌を呼ぶ
- パターン2 歌い手が既に歌っていて、歌の「レマーテ(remate)」のところで踊り始める
なんだか「リスト」にするほどのことではないのですが、どっちかのパターンで踊り始めます。
管理人は「パターン2」の方が好きなので、パターン2で入ることがめちゃめちゃ多いです。
でも、慣れないカンテさんとか、カンテさんのお考えなのか、踊り手が合図を出さないと歌わない~という人もいるので、その場合は「パターン1」でいきます。
カイーダの「10」の場所がわかる
カイーダは「caida」とスペイン語で書きます。
caer(カエール:落ちる)という動詞の名詞形で「落下」という意味です。
歌い手さんの歌が「落ちる」場所があります。それは、「歌が一区切りする」または「歌が終わる」ということを意味します。
このカイーダがわかって何をしなければならないか、というと次のことになります。
- パルマを叩いているなら、カイーダの「10」に向けて強めに叩いて、「10」でいったんパルマをシエレ(cierre:閉めるということ)します。
- 踊っているなら、カイーダが「歌の一区切り」なら、レマーテを入れる。
- 踊っているなら、カイーダが「歌の終わり」であれば、ハケ歌を呼ぶための「ジャマーダ」を入れる。
まずパルマですが、カイーダの「10」に向けてパルマを叩いて、「10」でパルマを止めることができるようになることが必要で、カイーダがあるときに、歌い手が「10」で終わっているのに、手拍子を「11、12」と叩いてしまうと、「あれ?」となります。
また、カイーダがわかると「歌の一区切り」や「歌の終わり」の場所が分かることになります。
歌がまだ続きそうだな~のカイーダのところは「歌の一区切り」なので、この部分はカンテさんが歌いませんので、踊り手がレマーテを入れるとかっこいいです。
そして、「歌の終わり」のカイーダの場合は、踊り手が「ジャマーダ」を入れるタイミング、ということになります。
カイーダで落ちるところに合わせて「6,7,8,9,10」のジャマーダを入れられるとかっこいいです。
わからない場合は、「歌が終わったな」と思ったら、自分のよきタイミングでジャマーダを入れればOKです!
ただ、ジャマーダを入れないといつまで経っても自分の位置に戻れないので、永遠にブレリアを踊ることになってしまう…
ジャマーダを入れて「ハケ歌」を呼んで、ブレリアの輪の中から自分の元のポジションの戻っていく、ということになります!
それでは動画で実例を見てみよう。
ではでは、動画で見てみましょう。
これは昨年に管理人がお誘いいただきましたライブですが、その最後のフィエスタブレリアです~
- 0:07 ギターさんの前奏(カンテさんをなんとなく見てますよね!)
- 0:19 カンテさんが「サリーダ」(出だし)を歌い始めます
- 0:29 カンテさんがかっこいいサリーダを歌っていて、そのちょっとした切れ目があったときに「ハレオ」を入れています!(なお、ハレオは必ずしも「切れ目」にいれなくっても大丈夫です。)
- 0:33 ここがいわゆる「カイーダ」です。下がってますよね!なので、「あ、落ちるな~」と思ったら、この節の「10」に合わせてパルマを強めに打って、10でパルマを〆ている、というカンジです。
- 0:49 いわゆる上記の「パターン2」で管理人が踊り始めております。カイーダだから、一区切りあるなと思ったので、ここで踊り始めております。
- 1:05あたり これが「歌が終わる」のカイーダなので、終わったところで管理人がジャマーダ入れております。これをすると、歌い手さんが「ハケ歌」を歌ってくれます!
- 1:15あたり ここから「ハケ歌」なので、自分の元の場所に戻っていく、という流れになります。
パターン1の動画を見てみましょう!
すばらしご活躍をされている先生の発表会の映像がYouTubeにありましたので、添付させていただきます。
- 0:12 カンテさんのサリーダが終わって、踊り手さんが輪に入り始めます。
- 0:17 踊り手さんがジャマーダを入れて、歌を呼んでいます(パターン1)
- 0:28 踊り手さんが「レマーテ」を入れています
- 0:46 カイーダにて、踊り手さんが「ハケ歌」を呼ぶジャマーダを入れています
- 0:52 ハケ歌で戻ります!ハケ歌で戻るときも、やはり「10」で閉めていますよね!
そしてもう1つ。
出だしからギターさんがかっこよく弾いておりますが、0:40くらいまでギターさんが弾いています。
ここはギターさんの「番」だから、この状況のときに、踊り手が踊り始めるということはないです。
ここで踊り始めちゃうと、あんまりわかってないのかな?というカンジになっちゃう、ということです。
0:47 くらいに、こんどは立ち上がって歌い手さんが歌を歌っています。この動画は歌い手さんの歌が4分ほどまで続きますが、その間は踊り手が踊るということはないですよね!
こんなカンジです。
いろいろ書いてみましたが、いずれにしても動画を見るときに、あ、自分ならここでジャマーダ入れるか~とか思いながら観ると勉強になると思います!